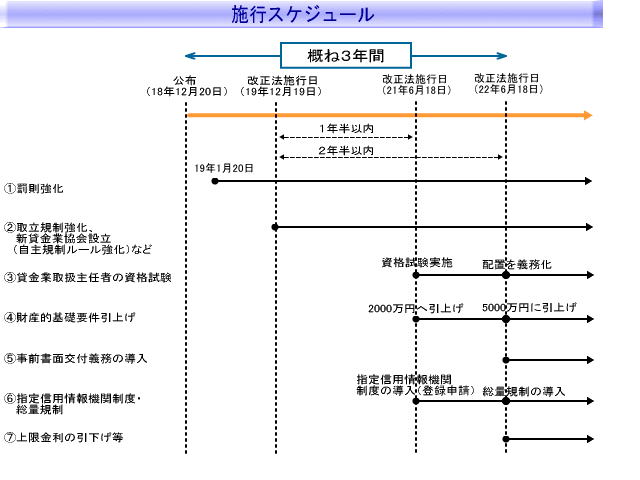| �@ | ||||
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ŗ@�������� | ||||
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ٌ�m�@���ŗ��m | ||||
| �@ | ||||
| �@�P�A���� �@�@�`�A�w�i �@�@�@�@�@���Ǝ҂ɂ�閳�S�ۖ��ۏ̏���Ҍ����ݕt�́A�ݕt�c���� �@�@�@�@�@�P�S�D�Q���~�A���p�Ґ���P�C�S�O�O���l�i���@�����j �@�@�@�@�@�@�@�ؓ���T���ȏ�̑��d���҂͖�Q�R�O���l�i���@�����j �@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȕj�Y�҂͖�P�W�D�S���l�i�����P�V�N�j �@�@�a�A�����̍��q �@�@�@�@�@���d�����̉����̏d�v���y�ё��Ƃ��䂪���̌o�ώЉ�� �@�@�@�@�@�����ĉʂ��������ɂ��݁A���Ƃ̓o�^�̗v���̋����A���� �@�@�@�@�@����y�ё��Ɩ��戵��C�҂ɌW�鐧�x�̊g�[���тɎw��M�p��� �@�@�@�@�@�@���x�̑n�݂��s���ƂƂ��ɁA���Ǝ҂ɂ��ߏ�ݕt���ɌW�� �@�@�@�@�@�K���̋������s���ق��A�݂Ȃ��ٍϐ��x�̔p�~�A�ƂƂ��ċ��K�� �@�@�@�@�@�ݕt�����s���҂��ݕt�����s���ꍇ�̏�������̈������A�ƂƂ��� �@�@�@�@�@�s���������������̍߂̑n�݁A�����Ƃ݂Ȃ������͈̂̔͂ɌW�� �@�@�@�@�@�K��̐��������s��ꂽ �@�@�b�A����̉����̖ړI�́A���d���҂��o���Ȃ����� �@�@�@�@�@���Ƃ̋Ɩ��̓K���� �@�@�@�@�@�ߏ�ݕt�̗}�� �@�@�@�@�@�@�@�w��M�p���@���x�A���ʋK�����A�ԍϔ\�͂��� �@�@�@�@�@�@�@�ؓ����}���A��������̈����� �@ �@�Q�A���Ƃ̋K�����Ɋւ���@���̈ꕔ�����i�����P�X�N�P���P�X���Ɏ{�s�j �@�@�@�@���o�^�c�Ƃ̔������T�N�ȉ��̒��͂P�疜�~�ȉ��̔������� �@�@�@�@�P�O�N�ȉ��̒��͂R�疜�~�ȉ��̔����Ɉ����グ�邱�Ɠ��A �@�@�@�@���������グ�� �@�@�@�@�i���Ɩ@��47���`��49���A��51���W�j �@�@�@�@�@�@���~���Z��̋��� �@ �@�R�A���Ƃ̋K�����Ɋւ���@���̈ꕔ�����i�����P�X�N�P�Q���P�X���Ɏ{�s�j �@�@�`�A�薼�� �@�@�@(1) �薼�̉��� �@�@�@�@�@�@���Ƃ̋K�����Ɋւ���@���̑薼���u���Ɩ@�v�ɉ��߂� �@�@�@(2) �ړI�̉��� �@�@�@�@�@�@�ړI�K��Ɂu���Ƃ��䂪���̌o�ώЉ�ɂ����ĉʂ��������� �@�@�@�@�@�@���݁v�������� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��P���j �@�@�a�A���Ǝ҂̓o�^�v���̋��� �@�@�@�@�@���Ǝ҂̓o�^���ۗv���ɁA���Ɍf������̂������� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��U���j �@�@�@�@�C�@���Ƃ�I�m�ɐ��s���邽�߂̕K�v�ȑ̐�����������Ă���� �@�@�@�@�@�@�F�߂��Ȃ��� �@�@�@�@���@���ɉc�ދƖ������v�ɔ�����ƔF�߂���� �@�@�b�A�s�K���̋����� �@�@�@(1) �Ɩ��^�c�Ɋւ���[�u �@�@�@�@�@�@���Ǝ҂́A���̑��Ƃ̋Ɩ��Ɋւ��Ď擾�����������v�ғ��� �@�@�@�@�@�@�ւ�����̓K���Ȏ戵���A�Ɩ����O�҂Ɉϑ�����ꍇ�ɂ����� �@�@�@�@�@�@���Y�Ɩ��̓I�m�Ȑ��s���̑����Ƃ̋Ɩ��̓K�ȉ^�c���m�ۂ��� �@�@�@�@�@�@���߂̑[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��12���̂Q�j �@�@�@�@�@�@�@�@�����Ǘ��ӔC�����߂�d�v�ȏ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���v���C�A���X�̓O������߂�� �@�@�@(2) �֎~�s�ׂ̋��� �@�@�@�@�@�@���Ǝ҂́A���̑��Ƃ̋Ɩ��Ɋւ��A���Ɍf����s�ׂ����Ă� �@�@�@�@�@�@�Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��12���̂U�j �@�@�@�@�C�@�������v�ғ��ɑ��A���U�̂��Ƃ������A���͑ݕt���̌_��̓��e �@�@�@�@�@�@�̂����d�v�Ȏ����������Ȃ��s�� �@�@�@�@���@�������v�ғ��ɑ��A�s�m���Ȏ����ɂ��Ēf��I���f����A �@�@�@�@�@�@���͊m���ł���ƌ�F�����邨����̂���s�� �@�@�@�@�n�@�ۏؐl�ƂȂ낤�Ƃ���҂ɑ��A�傽����҂��ٍς��邱�Ƃ� �@�@�@�@�@�@�m���ł���Ɖ������邨����̂��邱�Ƃ�������s�� �@�@�@�@�j �U�肻�̑��s�����͒������s���ȍs�� �@�@�@(3) �����ی��_��̒����ɌW�鐧�� �@�@�@�@�@�@���Ǝ҂ɂ����̎��E��ی����̂Ƃ��鐶���ی��̕t�ۂ� �@�@�@�@�@�@�֎~���� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��12���̂V�j �@�@�@�@�@�@�@�@���Ǝ҂��A��蓙�̎��E�ɂ��ی������x������ی��_��� �@�@�@�@�@�@�@�@�������邱�Ƃ��֎~ �@�@�@(4) �J�E���Z�����O�@�ւ̏Љ� �@�@�@�@�@�@���Ǝ҂́A�������v�ғ��̗��v�̕ی�̂��߂ɕK�v�ƔF�߂��� �@�@�@�@�@�@�ꍇ�ɂ́A�������v�ғ��ɑ��āA�J�E���Z�����O�@�ւ��Љ�� �@�@�@�@�@�@�悤�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��12���̂W�j �@�@�@(5) ���U�ɌW��K���̋��� �@�@�@�@�@�@���Ǝ҂́A�������v�ғ��̒m���A�o���A���Y�̏y�ёݕt���� �@�@�@�@�@�@�_��̒����̖ړI�ɏƂ炵�ĕs�K���ƔF�߂��銩�U���s���Ď��� �@�@�@�@�@�@���v�ғ��̗��v�̕ی�Ɍ����A���͌����邱�ƂƂȂ邨���ꂪ�Ȃ� �@�@�@�@�@�@�悤�ɁA���Ƃ̋Ɩ����s��Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��16���R���j �@�@�@�@�@�A���Ǝ҂́A�ݕt���̌_��̊��U�����������v�ғ������Y�_��� �@�@�@�@�@�@�������Ȃ��|�̈ӎv��\�������ɂ�������炸�A���Y���U���p�����Ă� �@�@�@�@�@�@�Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��16���S���j �@�@�@(6) �����ی��_��ɌW�铯�ӑO�̏��ʂ̌�t �@�@�@�@�@���Ǝ҂��A�ݕt���̌_��̑�������͑�����ƂȂ낤�Ƃ���҂̎��S�� �@�@�@�@�@����ĕی����z�̎x�������邱�Ƃ��߂�ی��_���������悤�� �@�@�@�@�@����ꍇ�ɂ����āA�����̎҂��瓯�ӂ悤�Ƃ���Ƃ��́A���炩 �@�@�@�@�@���߁A���Y�ی��_��̓��e��������鏑�ʂ���t���Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��16���̂R�j �@�@�@(7) ���ʌ�t�ɌW��K��̐��� �@�@�@�@�@�@�A�ѕۏؐl�ɂ��āA���O���ʋy�ь_�ʂɁA�Í��̍R�ٌ��y�� �@�@�@�@�@�@�����̍R�ٌ����Ȃ��|�̋L�ڂ��`���Â��� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��16���̂Q��P���A��17���R���j �@�@�@�@�@�@�@�@�A�ѕۏؐl�̕ی��O�ꂷ�邽�� �@�@�@�@�@�A�ݕt���ɌW��_��̂����A�������v�҂ł���ڋq�ɂ�肠�炩���� �@�@�@�@�@�@��߂�ꂽ�����ɏ]�����ԍς��s���邱�Ƃ������Ƃ��āA���Y�ڋq�� �@�@�@�@�@�@�����ɉ����A�ɓx�z�̌��x���ɂ����đݕt�����s�����Ƃ�邱�Ƃ� �@�@�@�@�@�@�u�ɓx������{�_��v�Ƃ��A�ɓx������{�_�ɂ��Ă̌_�ʂ� �@�@�@�@�@�@�L�ڎ����ɌW��K������� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��Q���A��17���j �@�@�@�@�@�B���������@�̏�������ȉ��̋����ł̑ݕt���ɂ��āA������̓��ӂ� �@�@�@�@�@�@�����ɁA�}���X���[�X�e�[�g�����g�ɂ���y�я��ʌ�t�̓d�q���� �@�@�@�@�@�@�\�Ƃ��� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��17���U���A��V���A��18���R���A��S���j �@�@�@(8) ���돑�ނ̉{�� �@�@�@�@�@�@���Ǝ҂́A���ғ����璠��̉{�����͓��ʂ𐿋����ꂽ�Ƃ��́A �@�@�@�@�@�@���ғ��̌����̍s�g�Ɋւ��钲����ړI�Ƃ�����̂łȂ����Ƃ� �@�@�@�@�@�@���炩�ł���Ƃ��������A���̐��������ނ��Ƃ��ł��Ȃ� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��19���̂Q�j �@�@�@(9) �����؏��ɌW��K���̋����i���Ɩ@��20���j �@�@�@�@�@�@���Ƃ��c�ގ҂́A���������@�̗����̐����z����ݕt���̌_��� �@�@�@�@�@�@���āA�����؏��̍쐬�����ؐl�ɏ������Ă͂Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@�@���������@�̋�������ݕt���̌_��ɂ��Č����؏��̍쐬�� �@�@�@�@�@�@�@�@�������֎~ �@�@�@�@�@�A���Ƃ��c�ގ҂́A�����؏��̍쐬�����ؐl�ɏ�������ϔC����擾 �@�@�@�@�@�@���Ă͂Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@�@�����؏��쐬�ɂ�����ϔC��̎擾���֎~ �@�@�@�@�@�B���Ǝ҂́A�����؏��̍쐬�����ؐl�ɏ�������ꍇ�ɂ́A���炩���߁A �@�@�@�@�@�@�����؏��ɂ�蒼���ɋ������s�ɕ����邱�ƂƂȂ�|���ɂ��āA���� �@�@�@�@�@�@����t���Đ������Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@(10)�旧�ċK���̋��� �@�@�@�@�@�@�v�����q�ϓI�Ȃ��̂Ƃ���ƂƂ��ɁA���̋֎~�s�ׂ̗ތ^��lj����� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��21���P���j �@�@�@�@�C�@���ғ�����ٍϓ��̎����ɂ��Đ\���o���Ă���ꍇ�ɂ����āA �@�@�@�@�@�@�����ȗ��R�Ȃ��A�����ɓd�b�A�K�ⓙ�ɂ��旧�Ă��s������ �@�@�@�@�@�@�@�@��Ԃɉ����ē����̎��X�Ȏ旧�s�ׂȂǁA�旧�K�������� �@�@�@�@���@���ғ�����ދ����ׂ��ӎv�������ꂽ�ɂ�������炸�A�����Ζ� �@�@�@�@�@�@�擙����ދ����Ȃ����� �@�@�@�@�n�@�֎~�s�ׂ̂����ꂩ���s�����Ƃ������邱�� �@�@�c�A�ē̋��� �@�@�@(1) �Ɩ����P���߂̑n�� �@�@�@�@�@�@���t������b���͓s���{���m���́A���̓o�^�������Ǝ҂̋Ɩ��� �@�@�@�@�@�@�^�c�Ɋւ��A�������v�ғ��̗��v�̕ی��}�邽�ߕK�v������ƔF�߂� �@�@�@�@�@�@�Ƃ��́A���Y���Ǝ҂ɑ��āA���̕K�v�̌��x�ɂ����āA�Ɩ��̕��@ �@�@�@�@�@�@�̕ύX���̑��Ɩ��̉^�c�̉��P�ɕK�v�ȑ[�u�𖽂��邱�Ƃ��ł��� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��24���̂U�̂R�j �@�@�@�@�@�@�@�@�K���ᔽ�ɔ����ċ@���I�ɑΏ����邽�߁A�o�^�����Ɩ���~�� �@�@�@�@�@�@�@�@�����A�Ɩ����P���߂� �@�@�@(2) �s�������̋����� �@�@�@�@�@�@���Ƃ̋Ɩ��Ɋւ��@�ߖ��͖@�߂Ɋ�Â����t������b�Ⴕ���͓s�� �@�@�@�@�@�@�{���m���̏����Ɉᔽ�����Ƃ��́A���Y���Ǝ҂ɑ��āA�o�^����� �@�@�@�@�@�@�����A���͋Ɩ��̑S���Ⴕ���͈ꕔ�̒�~�𖽂��邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ� �@�@�@�@�@�@���A���Y�s�ׂ���������̉�C�𖽂��邱�Ƃ��ł��� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��24���̂U�̂S�j �@�@�@�@�@�@�@�@�s�������̑Ώۂ��g�� �@�@�@(3) �Ɩ��J�n�`���i�x���Ǝ҂̔r���j �@�@�@�@�@�@�����ȗ��R���Ȃ��̂ɁA�o�^����������U���ȓ��ɑ��Ƃ��J�n�� �@�@�@�@�@�@�Ȃ��Ƃ��A���͈��������U���ȏ���Ƃ��x�~�����Ƃ��́A���t���� �@�@�@�@�@�@��b���͓s���{���m���́A�o�^�����������Ƃ��ł��� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��24���̂U�̂U�j �@�@�@(4) ���ƕ���o�`���̑Ώ۔͈͂��g�� �@�@�@�@�@�@�S�Ă̑��Ǝ҂Ɏ��ƕ��̒�o���`���Â��� �@�@�@�@�@�@�i���Ɩ@��24���̂U�̂X�j �@�@�@�@�@�@�@�@�����O�� 500���~���̑ݕt�c����������Ǝ҂Ɍ��� �@�@�d�A���Ƌ���i���Ɩ@��25���`��41����12�j �@�@�@(1) ���Ƌ�����A���t������b�̔F���đ��Ǝ҂��ݗ�����@�l�Ƃ��A �@�@�@�@�@�s���{�����ƂɎx����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@�]���̑S�����Ƌ���A����́A���v�@�l �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����͔C�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ǝ҂ւ̐��ٗ͂��ア �@�@�@�@�@�@�@�V�����F�@�l�̑��Ƌ���ݗ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@������Ǝ҂̉����𑣂��d�g�݂� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Ǝ҂ւ̐��ٗ͂����� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�P�Ȃ�ƊE�c�̂ł͂Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����p�̃V�X�e�� �@�@�@(2) ���Ƌ���́A���Ɍf���鎖�����ɂ��āA�Ɩ��K�����߂邱�ƂƂ��A �@�@�@�@�@�Ɩ��K���͓��t������b�̔F���� �@�@�@�@�C�@�ߏ�ݕt���̖h�~�Ɋւ��鎖�� �@�@�@�@���@�ɓx������{�_��ɂ�����~�j�}���y�C�����g�Ɋւ��鎖�� �@�@�@�@�@�@�@���{�_��̍Œ�ԍϊz �@�@�@�@�@�@�@�@�@�ؓ�����Ԃ������Ȃ��Ă��܂����i�� �@�@�@�@�n�@�L���̓��e�A���@�A�p�x�y�ѐR���Ɋւ��鎖�� �@�@�@�@�@�@�@�e���r�b�l�̕p�x�� �@�@�@�@�j�@���U�Ɋւ��鎖�� �@�@�@�@�z�@�J�E���Z�����O�Ɋւ��鎖�� �@�@�@(3) ���Ƌ���́A���̒芼�ɂ����āA��������A�@�ߓ��Ɉᔽ����s�ׂ� �@�@�@�@�@�����ꍇ�ɁA���Y������ɑ��A�ߑӋ����ۂ��A�芼�̒�߂鋦����� �@�@�@�@�@�����̒�~�Ⴕ���͐����𖽂��A���͏�������|���߂Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@(4) ���t������b���͓s���{���m���́A���̓o�^�������Ǝ҂ł����� �@�@�@�@�@���Ƌ���ɉ������Ă��Ȃ����̂̑��Ƃ̋Ɩ��ɂ��āA�������v�� �@�@�@�@�@���̗��v�̕ی�Ɍ����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A���Ƌ���̒芼�A�Ɩ��K�� �@�@�@�@�@���̑��̋K�����l�����A�K�Ȋē��s��Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��24���̂U��11�j �@ �@�S�A���Ɩ@�̈ꕔ�����i�����Q�P�N�U���P�W���Ɏ{�s�j �@�@�`�A���Y�I��b�v���̈��グ �@�@�@�@�@���Ǝ҂����Ƃ̋Ɩ���K���Ɏ��{���邽�ߕK�v���K���ȍŒᏃ���Y �@�@�@�@�@�̊z���Q�疜�~�������Ȃ����߂Œ�߂���z�Ƃ��� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��U���P����14���A��R���A��S���j �@�@�@�@�@�@�@����́A�@�l 500���~�A�l 300���~ �@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃւ̎Q�������̌��i�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@����������������ɁA�T�疜�~�Ɉ��グ�@�i�K�I�Ɉ��グ �@�@�a�A���Ɩ��戵��C�Ҏ��i�������x�i���Ɩ@��24���̂W�`��24����50�j �@�@�@(1) ���t������b�́A���Ɩ��戵��C�Ҏ��i�������s��Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@(2) ���t������b���������{�@�ւ��w�肷�� �@�@�@(3) ���i�����ɍ��i�����҂́A���Ɩ��戵��C�҂̓o�^��\�����A���t���� �@�@�@�@�@��b���o�^���� �@�@�@�@�@�@�@���݂́A�@�茤�C �@�@�b�A�w��M�p���@���x�̑n�� �@�@�@(1) ���t������b�ɂ��M�p���@�ւ̎w�萧�x�A�w��̗v���A�����̌��E�� �@�@�@�@�@�F���A��E�����̔閧�ێ��`���� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��41����13�`��41����16�j �@�@�@�@�@�@�@�M�p���̓K�ȊǗ���S���o�^�Ȃǂ̏��������M�p���@�ւ� �@�@�@�@�@�@�@�w�肷�鐧�x�����A���Ǝ҂����̑��ؓ��c����c���ł��� �@�@�@�@�@�@�@�d�g������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�ߏ�ݕt�̗}�� �@�@�@�@�@�@�@�̐��̐��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�M�p����K�ɊǗ����Ă��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@��薈�ɐM�p���̖����s���Ă��� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�������Ǝ҂���̐M�p���̒����₩�ɍs���� �@�@�@(2) �w��M�p���@�ւɑ��錓�Ƃ̏��F���A�Ɩ��K���̔F���A������ �@�@�@�@�@�Ǝ҂ɑ���ē`���A���̎w��M�p���@�ււ̏��`�����̑� �@�@�@�@�@�̎w��M�p���@�ւ̋Ɩ� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��41����17�`��41����26�j �@�@�@�@�@�@�@�w��M�p���@�ւ������̏ꍇ�A���݂Ɏc����̌𗬂��`�� �@�@�@�@�@�@�@�Â��� �@�@�@(3) ���t������b�ɂ��w��M�p���@�ւɑ�������A���������A �@�@�@�@�@�Ɩ����P���߁A�w��̎�������̑��̊ē� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��41����27�`��41����34�j �@�@�@(4) �������Ǝ҂ɑ�������w��M�p���@�ււ̏��`���A��� �@�@�@�@�@�ɌW�鎑�����v�ғ��̓��ӂ̎擾�`���A�����M�p���� �@�@�@�@�@�ړI�O�g�p���̋֎~�� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��41����35�`��41����38�j �@ �@�T�A�݂����Ƃ̈ꕔ�����i�����Q�Q�N�U���P�W���Ɏ{�s�j �@�@�`�A���Ɩ��戵��C�҂̕K�u�� �@�@�@�@�@���Ǝ҂ɑ��A�c�Ə����͎��������ƂɁA���i�����ɍ��i���o�^�� �@�@�@�@�@�����Ɩ��戵��C�҂�ݒu���� �@�@�@�@�@�ݒu���Ă��Ȃ����Ƃ�o�^���ۗv���Ƃ��� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��S���P����U���A��U���P����13���A��12���̂R�j �@�@�@�@�@�@�@���Ƃւ̎Q�������̌��i�� �@�@�@�@�@�@�@�@�ߏ���̂��߂̎w���E�������s�� �@�@�a�A���Y�I��b�v���̈��グ �@�@�@�@�@���Ǝ҂����Ƃ̋Ɩ���K���Ɏ��{���邽�ߕK�v���K���ȍŒᏃ �@�@�@�@�@���Y�̊z���T�疜�~�������Ȃ����߂Œ�߂���z�Ƃ��� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��U���P����14���A��R���A��S���j �@�@�@�@�@�@�@���ݖ�14,000�̑��Ǝҁi����18�N�R�������_�̓o�^�Ǝҁj�̂����A �@�@�@�@�@�@�@�����Y�z�T�疜�~�ȏ�̂��̂́A�� 3,700�Ǝ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃւ̎Q�������̌��i�� �@�@�b�A�s�K���̋����� �@�@�@(1) �����̐����z����_��̋֎~�� �@�@�@�@�@���Ǝ҂́A���������@���闘���̌_���������A��������̂��A �@�@�@�@�@���͂��̎x����v�����Ă͂Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��12���̂W�j �@�@�@(2) ���ʌ�t�`���̋��� �@�@�@�@�@���Ǝ҂́A�ݕt���ɌW��_����������܂łɁA���Y�_��̓��e����� �@�@�@�@�@���鏑�ʂY�_��̑�����ƂȂ낤�Ƃ���҂Ɍ�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�i���Ɩ@��16���̂Q�j �@�@�@�@�@�@�@�ݕt���ɂ�����A�g�[�^���̌������S�z�Ȃǂ�����������ʂ̎��O��t �@�@�@�@�@�@�@���`���Â� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���O���ʌ�t�`������ �@�@�c�A�ߏ�ݕt���ɌW��K���̋��� �@�@�@(1) �ԍϔ\�͂̒����`���i���Ɩ@��13���j �@�@�@�@�@�@���Ǝ҂ɑ��A�ݕt���̌_���������悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A�ڋq���� �@�@�@�@�@�@�ԍϔ\�͂̒������`���Â��� �@�@�@�@�@�@�@�@���݂͓w�͋`���@���@�V���x�ł́A�ᔽ�͍s�������̑Ώ� �@�@�@�@�@�A���Ǝ҂ɑ��A�l�ł���ڋq���Ƒݕt���̌_���������悤�Ƃ��� �@�@�@�@�@�@�ꍇ�ɂ́A�w��M�p���@�ւ��ۗL����M�p�����g�p�����������`�� �@�@�@�@�@�@�Â��� �@�@�@�@�@�@�@�@�l�����̏ꍇ �@�@�@�@�@�B���Ǝ҂ɑ��A����̑ݕt���̋��z���T�O���~����ݕt���ɌW�� �@�@�@�@�@�@�_�͎���̑ݕt���̋��z�Ƒ��̑��Ǝ҂̑ݕt���̎c���̍��v�z�� �@�@�@�@�@�@�P�O�O���~����ݕt���ɌW��_����������ꍇ�ɂ́A�����[ �@�@�@�@�@�@���̒�o���邱�Ƃ��`���Â��� �@�@�@(2) �ߏ�ݕt���̋֎~�i���Ɩ@��13���̂Q�`��13���̂S�j �@�@�@�@�@�@���Ǝ҂ɑ��A�ڋq���̕ԍϔ\�͂���ݕt���̌_��̒������֎~ �@�@�@�@�@�@ ���� �@�@�@�@�@�A���Ǝ҂ɑ��A����̑ݕt���̋��z�Ƒ��̑��Ǝ҂̑ݕt���̎c���� �@�@�@�@�@�@���v�z���N�����̂R���̂P���邱�ƂƂȂ�ݕt���������֎~���� �@�@�@�@�@�@�@�@�����̌��ʁA���ؓ��c�����N���̂R���̂P����ݕt���ȂǁA �@�@�@�@�@�@�@�@�ԍϔ\�͂����ݕt�����֎~���� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R���̂P���킴�킴�@���ɂ��āA�������݂��� �@�@�@�@�@�@�@�@�R���̂P���Ă��A���̕ԍϔ\�͂���^�I�ɔF�߂��A���S�� �@�@�@�@�@�@�@�@�����j�[�Y�ƔF�߂���ꍇ�ɂ́A��O�I�Ɏؓ����F�߂� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z��[���͑��ʋK���̑ΏۊO �@�@�@�@�@�B�ɓx������{�_���������Ă���ꍇ�ɂ́A�ɓx�����ݕt���̏� �@�@�@�@�@�@���Ă��A���͒���I�ɁA�w��M�p���@�ւ̐M�p�����g�p���ĕԍ� �@�@�@�@�@�@�\�͂����A����̑ݕt���̋��z�Ƒ��̑��Ǝ҂̑ݕt���̎c���� �@�@�@�@�@�@���v�z���N�����̂R���̂P����ƔF�߂���Ƃ��́A�ɓx������ �@�@�@�@�@�@�t����}�����邽�߂ɕK�v�ȑ[�u���u���Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�d�A�݂Ȃ��ٍϐ��x�̔p�~�i���Ɩ@��43���폜�j �@�@�@�@�@���Ǝ҂̍s�����K����ݎ،_��Ɋ�Â����҂����������@��P�� �@�@�@�@�@��P���ɋK�肷�闘���̐����z�Əo���@��T���Q���ɋK�肷�闘���� �@�@�@�@�@�����z�Ƃ̊Ԃ̋�����C�ӂɎx�����A���Ǝ҂���_�ʓ�����t �@�@�@�@�@����Ă���ꍇ�ɂ́A���Y�x�����͗L���ȍ��ٍ̕ςƂ݂Ȃ����Ƃ� �@�@�@�@�@���Ă���K���p�~������Ɩ@��́u�݂Ȃ��ٍρv���x�i�O���[�]�[ �@�@�@�@�@�������j��p�~ �@ �@�U�A���������@�̈ꕔ�����i�����Q�Q�N�U���P�W���Ɏ{�s�j �@ �@�@�`�A�����̐��� �@�@�@�@�@���҂��ƂƂ��čs�����K����ݎ�����̓����ҊԂŕ�������ꍇ�� �@�@�@�@�@�����錳�{�z�敪�̓K�p�̓�����݂��� �@�@�@�@�@�i���������@��T���j �@�@�a�A�݂Ȃ������͈̔� �@�@�@�@�@���҂��ƂƂ��čs�����K����ݎɂ�����݂Ȃ������͈̔͂ɂ��ẮA �@�@�@�@�@�݂Ȃ��������珜�O������p���ȉ��̂��̂Ɍ��肷�� �@�@�@�@�@�i���������@��U���j �@�@�@�@�C�@�_��̒������͍��ٍ̕ς̔�p�ł����āA���Ɍf������� �@�@�@�@�@�@���d���� �@�@�@�@�@�A���̋@�ւ��s���葱�Ɋւ��Ă��̋@�ւɎx�����ׂ����� �@�@�@�@�@�B�`�s�l�萔���i���߂Œ�߂�z�͈͓̔��j �@�@�@�@�@�@�@�@�]�O�A�K�������͂����肵�Ă��Ȃ������Ƃ��낪�A���ׂĊ�{�I�� �@�@�@�@�@�@�@�@�����̊T�O�Ɋ܂܂�邱�ƂɂȂ��� �@�@�@�@�@�@�@�@�ƂƂ��čs���ݕt���̗����ɂ��ẮA�_�������p�y�э��ٍ� �@�@�@�@�@�@�@�@��p�̂����A���d���ہE�`�s�l�萔�����Ɍ��菜����� �@�@�@�@���@���҂̗v���ɂ����҂��s�������̔�p�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���� �@�@�b�A���s���s�ɂ�锅���z�̗\��̏�� �@�@�@�@�@���҂��ƂƂ��čs�����K����ݎɂ�������s���s�ɂ�锅���z�� �@�@�@�@�@�\��̏����N�Q���Ƃ��� �@�@�@�@�@�i���������@��V���j �@�@�c�A�ۏ� �@�@�@�@�@���҂��ƂƂ��čs�����K����ݎ؏�̍����傽����Ƃ���ƂƂ��� �@�@�@�@�@�s���ۏɂ����āA�ۏؐl���傽����҂����ׂ��ۏؗ��ɂ��A �@�@�@�@�@�傽����̗����ƍ��Z���ď�������K���̑ΏۂƂ���ق��A���ۏ� �@�@�@�@�@������ۏؗ��̓�����݂��� �@�@�@�@�@�i���������@��W���j �@�@�@�@�@�@�@�ݕt�����Ǝ�肪�ۏ؋Ǝ҂Ɏx�����ۏؗ������Z���ď�������� �@�@�@�@�@�@�@���߂����ꍇ�A���ߕ����ɂ��A�����Ƃ��āA�ۏؗ����Ƃ��A �@�@�@�@�@�@�@�ۏ؋Ǝ҂ɌY�������Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�ׂ����Ƃ���܂ŁA���m�ɂ��� �@ �@�V�A�o���̎����A�a����y�ы������̎����Ɋւ���@���̈ꕔ���� �@�@�@�i�����P�X�N�P���P�X���Ɏ{�s�j �@�@�`�A���� �@�@�@�@�@���K�̑ݕt�����s���҂��ƂƂ��ċ��K�̑ݕt�����s���ꍇ�ɂ����āA �@�@�@�@�@�N�P�O�X�D�T�����銄���ɂ�闘���̌_��������Ƃ��́A�P�O�N �@�@�@�@�@�ȉ��̒����Ⴕ���͂R�����~�ȉ��̔����ɏ����A���͂���Ȃ��� �@�@�@�@�@���̂Ƃ��A���Y�������銄���ɂ�闘������̂��A���͂��̎x�� �@�@�@�@�@��v�������҂����l�Ƃ��� �@�@�@�@�@�i�o���@��T���R���j �@ �@�W�A�o���̎����A�a����y�ы������̎����Ɋւ���@���̈ꕔ���� �@�@�@�i�����Q�Q�N�U���P�W���Ɏ{�s�j �@ �@�@�`�A���K�ݎؓ��̔}��萔���̐��� �@�@�@(1) ���K�̑ݎ̔}��萔���̐����Ɋւ��A�ݎ̊��Ԃ��P�N�����ł��� �@�@�@�@�@���̂ɂ��ẮA���Y�ݎ̋��z�ɁA���̊��Ԃ̓����ɉ����A�N�T�� �@�@�@�@�@�̊������悶�Čv�Z�������z����萔���̌_������A���͂���� �@�@�@�@�@������萔������̂��Ă͂Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�i�o���@��S���P���j �@�@�@(2) ���K�̑ݎ̕ۏ̔}��ɂ��Ă��A���K�̑ݎ̔}��� �@�@�@�@�@���l�̋K�����s�� �@�@�@�@�@�i�o���@��S���Q���j �@�@�a�A�ƂƂ��čs���������ᔽ�̍� �@�@�@�@�@�ƂƂ��čs���������ᔽ�̍߂ƂȂ�������A�N�Q�X�D�Q������ �@�@�@�@�@��������A�N�Q�O����������Ɉ��������� �@�@�@�@�@�i�o���@��T���Q���j �@�@�@�@�@�@�@��������̈����� �@�@�@�@�@�@�@�@�@������z����ꍇ�͌Y�������Ȃ� �@�@�@�@�@�@�@���������@�̏�������i20���`15���j�Əo���@�̏�������i20���j �@�@�@�@�@�@�@�̊Ԃ̋����ł̑ݕt���ɂ��ẮA�s�������̑ΏۂƂ��� �@�@�b�A���K�ݎ̕ۏؗ��̐��� �@�@�@�@�@���҂��ƂƂ��čs�����K����ݎ؏�̍����傽����Ƃ���Ƃ� �@�@�@�@�@���čs���ۏɂ����āA�ۏؐl���傽����҂����ׂ��ۏؗ� �@�@�@�@�@�ɂ��A�傽����̗����ƍ��Z���ď�������K���̑ΏۂƂ���܂��A �@�@�@�@�@�ۏؗ�������ꍇ�ɂ����鍂�����̋K���̓�����݂��� �@�@�@�@�@�i�o���@��T���̂Q�y�ё�T���̂R�j �@�@�c�A�݂Ȃ����� �@�@�@�@�@���K�̑ݕt�����s���҂����̑ݕt���Ɋւ�����K�́A���Ɍf���� �@�@�@�@�@���̂������A�����Ȃ閼�`�������Ă��邩���킸�A�����Ƃ݂Ȃ� �@�@�@�@�@�i�o���@��T���̂S��S���j �@�@�@�@�C�@�_��̒������͍��ٍ̕ς̔�p�ł��āA���Ɍf������� �@�@�@�@�@�@���d���� �@�@�@�@�@�A���̋@�ւ��s���葱�Ɋւ��Ă��̋@�ւɎx�����ׂ����� �@�@�@�@�@�B�`�s�l�萔�� �@�@�@�@���@�ݕt���̑�����̗v���ɂ��ݕt�����s���҂��s�������̔�p �@�@�@�@�@�@�Ƃ��Đ��߂Œ�߂���� �@ �@�X�A�o���̎����A�a����y�ы������̎����Ɋւ���@���̈ꕔ���������� �@�@�@�@���̈ꕔ�����i�����Q�Q�N�U���P�W���Ɏ{�s�j �@�@�@�@�������Ǝҋy�ѓd�b�S�ۋ��Z�ɂ��Ă̓���i 54.75���j��p�~���� �@�@�@�@�i�o���@�ꕔ�����@������W���`��16���폜�j �@ �@10�A���̑� �@�@�`�A���{�̓w�͋`�� �@�@�@�@�@���{�́A���d�����̉����̏d�v���ɂ��݁A�W�Ȓ����݊Ԃ� �@�@�@�@�@�A�g���������邱�Ƃɂ��A�������v�ғ����ؓ��ꖔ�͕ԍςɊւ��� �@�@�@�@�@���k���͏������̑��̎x�����邱�Ƃ��ł���̐��̐����A���� �@�@�@�@�@���v�҂ւ̎����̗Z�ʂ�}�邽�߂̎d�g�݂̏[���A��@�ȑ��Ƃ� �@�@�@�@�@�c�ގ҂ɑ�������̋����A���Ǝ҂ɑ��鏈�����̑��̊ē� �@�@�@�@�@�̌��A���̖@���ɂ����~��̋K��̎{�s�̌����̑� �@�@�@�@�@���d�����̉����Ɏ�����{��𑍍��I�����ʓI�ɐ��i����悤 �@�@�@�@�@�w�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ� �@�@�@�@�@�i������U�U���j �@�@�@�@�@�@�@���d���Җ��ɑ��鐭�{�����������g�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���{�́A�W�Ȓ����݂̘A�g�����ɂ��A���d�������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�̂��߂̎{��𑍍��I�����ʓI�ɐ��i���� �@�@�a�A�������i������U�V���j �@�@�@(1) ���{�́A���Ɛ��x�݂̍���ɂ��āA���̖@���̎{�s��Q�N�U���ȓ��ɁA �@�@�@�@�@���̖@���ɂ�������̋K��̎��{�A���Ǝ҂̎��ԓ������Ă��A �@�@�@�@�@��S���i���F��L�T�j�̋K��ɂ�������̋K����~���Ɏ��{���邽�߂� �@�@�@�@�@�u���ׂ��{��̕K�v���̗L���ɂ��Č����������A���̌����̌��ʂɉ��� �@�@�@�@�@�ď��v�̌��������s�����̂Ƃ��� �@�@�@(2) ���{�́A�o���̎����A�a����y�ы������̎����Ɋւ���@���y�ї��� �@�@�@�@�@�����@�Ɋ�Â������̋K���݂̍���ɂ��āA���̖@���̎{�s��Q�N�U�� �@�@�@�@�@�ȓ��ɁA���������̏��̑��̌o�ϋ��Z��A�ݕt���̗����̐ݒ�� �@�@�@�@�@���̑����Ǝ҂̋Ɩ��̎��ԓ������Ă��A��T���i���F��L�U�j�y�� �@�@�@�@�@��V���i���F��L�W�j�̋K��ɂ�������̋K����~���Ɏ��{���邽�߂� �@�@�@�@�@�u���ׂ��{��̕K�v���̗L���ɂ��Č����������A���̌����̌��ʂɉ��� �@�@�@�@�@�ď��v�̌��������s�����̂Ƃ��� |