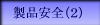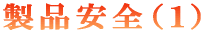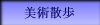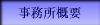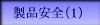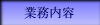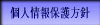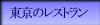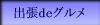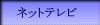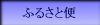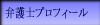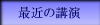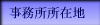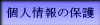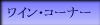
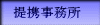
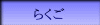
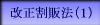
消費生活用製品安全法の改正(平成19年5月14日施行)
高 芝 法 律 事 務 所
弁護士 高 芝 利 仁
1、改正の経緯
近時においても、ガス瞬間湯沸器による一酸化炭素中毒死傷事故や家庭用シュレ
ッダーによる幼児の手指切断事故等のような重大な製品事故が発生している。
これらの事故では、メーカー等から国に事故報告がなされていなかったり、報告まで
に長期間経過しているものが少なからずあった。
このため、国が重大製品事故が発生した事実を的確に把握できず、その結果、消費
者への事故情報の周知や事故の再発防止を速やかに行えないケースも見られた。
このような状況を受け、今般、メーカー等に重大製品事故の報告を義務付ける消費
生活用製品安全法の一部を改正する法律が成立した。
2、重大製品事故
重大製品事故とは、次のものをいう(改正法第2条第5項、第4項)。
①一般消費者の生命または身体に対する危害が発生した事故のうち、危害が重大で
あるもの
死亡事故、重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)又は後遺
障害事故、一酸化炭素中毒事故
②消費生活用製品が滅失し、又はき損した事故であって、一般消費者の生命又は身
体に対する重大な危害が生ずるおそれのあるもの
火災(消防が火災として確認したもの)
3、製品事故の対象から除外される事故
(1) 消費生活用製品の欠陥によって生じたものでないことが明らかな事故は、製品事故
の対象から除外する(改正法第2条第4項)。
①自動的に対象外とすべきもの
故意に人体に危害を加えた場合(ex. 傷害事件に使用された包丁)
製品自体は健全に機能しているが、製品外の事故が生じた場合(ex. 追突事故
に遭った自転車)
②個別に判断を要するもの
一般消費者の目的外使用や重過失の場合等
(2) 事故報告の対象に当たるか否かを判断する第三者委員会を設置する。
安定的な運用のためにも、製品事故の対象から除外される事例の蓄積と公開が
期待される。
4、事故情報の報告の義務化
(1) 製造事業者または輸入事業者は、日本の市場に最初に製品を投入する者であるの
で、製品の安全性に一次的な責任を負う者とされる。
そこで、製造事業者または輸入事業者は、その製造または輸入した製品について重
大製品事故が生じたことを知ったときは、発生の事実を知った日から起算した10日
以内に、製品の名称および型式、事故の内容、製造または輸入した数量、販売した
数量を主務大臣に報告しなければならない(改正法第35条)。
報告項目は、事故発生日、被害の概要、事故の内容、製品の名称、機種・型式、製
造・輸入・販売数及びその時期、事故を知った契機と日、事故原因、事故への対応
等である。
重大製品事故以外の製品事故を知った場合は、独立行政法人製品評価技術基
盤機構(nite)に報告することになっている。
(2) 製品の小売販売事業者、修理事業者または設置事業者は、その事業に係る製品に
ついて重大製品事故が生じたことを知ったときは、その旨を製品の製造事業者また
は輸入事業者に通知するよう努めなければならない(改正法第34条2項)。
(3) 報告義務の対象となる製品としては、他の法令により個別に規制されているもの(例
えば、自動車、化粧品、医薬品等)を除いた消費生活用製品を広く対象とする。
電池など、通常、機械とは別に売買されるものは、原則として、単体の製品として
扱われる。
OEMについては、原則として、実質的に製造している者が製造事業者となる。
なお、海外で起きた事故は、報告義務の対象とはされない。
5、主務大臣への報告と民事上または刑事上の責任
改正法の事故報告制度においては、報告の対象となることと製品の欠陥があることと
は直結しておらず、製造事業者または輸入事業者が主務大臣に事故報告を行った
事実をもって、直ちに、民事上または刑事上の責任を負うこととはならない。
6、主務大臣による事故情報の公表
(1) 経済産業省は、製造事業者又は輸入事業者から報告を受理してから1週間以内に、
製品一般名、事故概要、受理日、事故発生日(事業者名、型式名なし)をウェブサイ
トで公表する。
(2) 主務大臣は、報告を受けた事故情報をさらに分析し、当該事故に係る消費生活用製
品によって一般消費者の生命又は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止
するため必要があると認めるときは、経済産業省は、①製造事業者又は輸入事業者
に対し再発防止策を求めるとともに、②事業者名、機種・型式名、事故の内容、製造
事業者又は輸入事業者による再発防止策、消費者が再発防止のために留意すべき
事項等危険の回避に資する事項をウェブサイトで公表し、記者発表を行う(改正法第
36条第1項)。
なお、重大な危害の発生及び拡大を防止するため迅速に対応する必要がある場合
には、上記(1) を経ることなく、直ちに、上記の公表を行うことがある。
(3) 主務大臣は、製造事業者または輸入事業者が重大製品事故の報告を怠ったり又は
虚偽の報告をした場合において、その製造または輸入に係る製品の安全性を確保す
るため必要があると認めるときは、当該製造事業者または輸入事業者に対し、重大製
品事故に関する情報を収集、管理及び提供するために必要な体制の整備を命令ず
ることができる(改正法第37条)。
体制整備命令違反に対しては、1年以下の懲役または 100万円以下の罰金が科
される(併科もあり)(改正法第58条第5号)。
7、事業者の責務
(1) 製造事業者または輸入事業者は、その製造または輸入した製品に係る事故が生じた
場合には、製品事故が発生した原因に関する調査を行うとともに、必要な場合には、
当該製品の回収その他の措置をとるよう努めなければならない(改正法第38条第1項)。
(2) 販売事業者は、製造事業者又は輸入事業者が行う製品回収その他の危害の発生及
び拡大を防止するための措置について、当該製品の販売停止、在庫情報の提供等を
通じて、当該措置に協力するよう努めなければならない(改正法第38条第2項)。
危害防止命令(改正法第39条)等が発動されている場合は、販売事業者は製造事業
者または輸入事業者に協力しなければならない(改正法第38条第3項)。