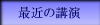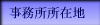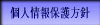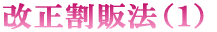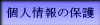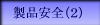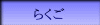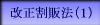
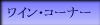
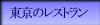
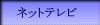
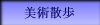
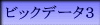


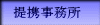
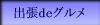
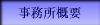
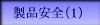

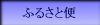
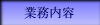

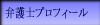
改正割賦販売法のポイント
高芝法律事務所
弁護士 高芝利仁
1、はじめに
改正割賦販売法第1条第1項は、「購入者等が受けることのある損害の防止」
すなわち「消費者被害の防止」を同法の目的の一つとして明確に位置づけました。
これに伴い、過剰与信の防止、個別クレジットにかかる加盟店調査義務や民事ル
ール等が整備されました。
2、クレジットの定義等の変更
a、クレジットの定義の変更
従来の割賦購入あっせんを「包括信用購入あっせん(包括クレジット)」と
「個別信用購入あっせん(個別クレジット)」とし、新たに「2カ月を超える
1回払、2回払」も規制対象としました(法第2条第3項、第4項)。1回払
も対象とすることとしましたので、「割賦購入あっせん」の用語は「信用購入
あっせん」に変更されました。包括クレジットは、従来総合方式と言われてい
たものやリボルビング方式を合わせた、いわゆるクレジットカード取引の総称
であり、個別クレジットは、従来個品方式と言われていたものです。ここで、
「2カ月を超える」とは、あらかじめ定められた支払日が契約日から「2カ月
を超える」場合をいいます(例えば、契約日が1月1日の場合、あらかじめ定
められた支払日が3月1日の場合は2カ月を超えていませんが、3月2日の場
合は2カ月を超えています)。そこで、翌月1回払(いわゆるマンスリークリ
ア)等、2カ月を超えないものは規制対象外となります。また、あらかじめ定
められた支払日は契約日から2カ月以内であったが、その引落日が金融機関の
休日であるなど、クレジット業者に関わらない事由によって、結果的に支払(
引落とし)が2カ月を超えることとなったような場合も規制対象外となると考
えられます。なお、金融業者が締結する金銭消費貸借契約と販売業者等が締結
する売買契約等の間に密接な牽連性が認められる場合は、当該金銭消費貸借契
約は、従来同様、クレジット契約とされます。
b、クレジット規制の対象の変更
消費者被害を未然に防止するため、クレジット規制の対象を不動産の販売を
除く全ての商品及び役務に拡大しました(法第2条、第35条の3の60)。
3、包括クレジット
a、包括支払可能見込額の調査
包括クレジット業者(クレジットカード業者)は、過剰与信防止のため、カ
ード等の交付や極度額の増額をする際、消費者の支払可能と見込まれる額(消
費者が居住用資産を処分することなく、また、必要最低限の生活維持費を支払
に充てることなく、クレジット債務を支払えると見込まれる一年間当たりの額)
を調査し、この額に一定の割合(0.9)を乗じた額を超えることとなるカー
ド等の交付や極度額の増額が禁止されます(法第30条の2、第30条の2の
2)。包括支払可能見込額の調査は、総合的、合理的に算定すべきものとされ、
その詳細は、経済産業省令で定められています(規第39条~第47条の2)。
そして、この義務を実効性あるものとするため、指定信用情報機関が創設され、
包括クレジット業者が支払能力調査を行う際には、この信用情報機関の利用が
義務付けられました(法第30条の2第3項)。なお、改正割賦販売法の過剰
与信防止義務は、支払能力を合理的な算定に基づくことなく過大に見積もって
多額の与信を行うことを禁止するものですので、一定の数値基準で判断するい
わゆる総量規制とは異なります。
b、業務の運営に関する措置
包括クレジット業者は、利用者等の利益の保護を図るために必要な措置を講
じなければなりません(法第30条の5の2、規第56条~第60条)。
4、個別クレジット
a、個別支払可能見込額の調査
個別クレジット業者は、過剰与信防止のため、個別クレジット契約を締結し
ようとする場合には、その契約の締結に先立って、消費者の支払可能と見込ま
れる額を調査し、この額を超える個別クレジット契約を締結することが禁止さ
れます(法第35条の3の3、4)。個別支払可能見込額の調査は、総合的、
合理的に算定すべきものとされ、その詳細は、経済産業省令で定められている
こと(規第71条~第73条の2)、この義務を実効性あるものとするため、
個別クレジット業者が支払能力調査を行う際には、指定信用情報機関の利用が
義務付けられたこと(法第35条の3の3第3項)等は、包括クレジットと同
様です。この規制は、個人の支払能力に着目した規制ですので、特定商取引法
が適用される取引か否かを区別することなく、対象とされます。
b、加盟店調査義務
改正割賦販売法は、従前の加盟店管理の考え方ではなく、加盟店調査の考え
方を採っています。この考えの下、個別クレジット業者は、消費者被害を未然
に防止するため、訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続
的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約(以下、特定契約といいます)
に係る個別クレジット契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先
立って、加盟店である販売業者等が勧誘をするに際して、不実告知、重要事実
の不告知、不退去、退去妨害等の不当な勧誘行為を行っていないかどうかを調
査しなければなりません(法第35条の3の5)。特定契約以外の取引につい
ては、健全な取引に対する過剰規制となる恐れもあることから、この義務の対
象とはされていません。調査の時期は、①加盟店契約を締結する場合(規第7
5条第1号)、②個別クレジット契約の申込みを受けた場合(規第75条第2
号)、③苦情の内容が特定商取引法の禁止行為等をしたことに起因すると認め
る場合等(規第77条第1項)です。上記②の調査は、個別クレジット契約の
申込みを受けた後、相当な期間をおいて、電話その他の方法により当該申込み
をした者に対して行います(規第76条第10項)。そして、個別クレジット
業者は、加盟店が不実告知等をしたと認めたときは、この勧誘の相手方と、当
該売買契約等に係る個別クレジット契約を締結してはならないとされています
(法第35条の3の7本文)。この調査義務や与信禁止の義務に違反した場合
は、個別クレジット業者は、改善命令を受ける可能性があるとともに(法第3
5条の3の21)、個別クレジット契約に関する民事ルール(取消等)との関
係で、消費者に既払金を返還しなければならなくなる可能性があります。なお、
加盟店(販売業者等)は、調査に協力するよう努めなければならないとされて
います(法第35条の3の6)。
c、個別クレジット業者による書面の交付
個別クレジット業者は、特定契約に係る個別クレジット契約の申込みを受け
たとき、契約を締結したときは、契約内容を確認する機会を提供するため、そ
れぞれの段階において、当該契約に関する事項を記載した書面(申込書面、契
約書面)を遅滞なく交付しなければなりません(法第35条の3の9)。ここ
で、「遅滞なく」は、合理的な事情を踏まえて、判断されると考えられます。
そして、個別クレジット業者は、申込書面に「販売契約の勧誘等についての調
査内容」を、契約書面に「その調査結果」を記載することになっています(法
第35条の3の9第2項第3号、第4項第3号)。
d、業務の運営に関する措置
個別クレジット業者は、購入者等の利益の保護を図るために必要な措置を講
じなければなりません(法第35条の3の20、規第89条~第94条)。
5、クレジットカード番号等の適切な管理
クレジットカード業者等は、クレジットの決済システムの信頼を維持するた
め、クレジットカード番号等が漏えい、滅失又はき損しないように適切な管理
のために必要な措置を講じなければなりません。また、クレジットカード業者
等は、クレジットシステムを提供する者として、加盟店、加盟店などからクレ
ジットカード番号等の取扱いの全部または一部の委託を受けた第三者等のクレ
ジットカード番号等を保有する業者がクレジットカード番号等を漏えい、滅失
又はき損しないよう、その業者に対して必要な指導その他の措置を講じなけれ
ばなりません(法第35条の16、規第132条、第133条)。
6、個別クレジット契約のクーリングオフ
a、クーリングオフ制度
訪問販売、電話勧誘販売、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契
約、業務提供誘引販売個人契約(以下、特定契約といいます)に係る個別クレ
ジット契約の申込みをした場合や契約を締結した場合、契約の申込者等は、一
定期間(8日ないし20日)、書面により、個別クレジット契約の申込みの撤
回又は解除を行うことができます(法第35条の3の10、11)。これは、金銭消
費貸借型の個別クレジット契約にも適用されます。起算日は、申込者等が個別
クレジット契約の書面を受領した日です。受領したことの立証責任は、個別ク
レジット業者にあります。クーリングオフ期間は、特定契約の種類によって異
なります。20日とすべきところを8日と記載すると不備書面とされ、クーリ
ングオフ期間は進行しません。また、クーリングオフ妨害があった場合にもク
ーリングオフ期間は進行しません。このような場合は、数か月後でも、クーリ
ングオフが可能となり、個別クレジット業者が既払金を返還しなければならな
い場合もありえます。
ところで、個別クレジット契約と販売契約等のそれぞれに独立のクーリング
オフ制度があると、申込者等は、双方に書面で意思表示をしなければならず、
消費者保護が十分とは言えません。また、通常の場合、申込者等は、個別クレ
ジット契約と販売契約等の双方をクーリングオフすることが一般と考えられま
す。そこで、個別クレジット契約がクーリングオフされた場合、個別クレジッ
ト業者は、販売業者等にその旨通知しなければならないとされています(法第
35条の3の10第4項、第35条の3の11第6項)。この場合、現に効力を有する
販売契約等もクーリングオフされたものとみなされます(法第35条の3の10第
5項、第35条の3の11第7項)。ここで、「現に効力を有する」販売契約等に
は、特商法のクーリングオフ期間を経過したものも含まれると考えられますの
で、留意が必要です。そこで、申込者等は、個別クレジット契約と販売契約等
の双方をクーリングオフしたい時は、個別クレジット業者の方にだけ書面を送
れば足りることになります。但し、申込者等が、個別クレジット契約はクーリ
ングオフしたいが、販売契約等は維持し、現金払したい場合は、個別クレジッ
ト契約のクーリングオフの書面において、その旨個別クレジット業者に通知す
れば、販売契約等のクーリングオフの効力は発生しないとされています(法第
35条の3の10第5項但書、第35条の3の11第7項但書)。
b、クーリングオフの効果
個別クレジット契約がクーリングオフされ、かつ、販売契約等もクーリング
オフされたものとみなされた場合は、販売業者等は立替払金を個別クレジット
業者に返還し(法第35条の3の10第8項、第35条の3の11第10項)、個別クレ
ジット業者は、申込者等に既払金を返還しなければなりません(法第35条の3
の10第9項、第35条の3の11第11項)。但し、販売業者等に直接支払われた頭
金等は、販売業者等が返還します(法第35条の3の10第13項、第35条の3の11
第14項)。
なお、上記により、現に効力を有する販売契約等もクーリングオフされたも
のとみなされた場合、「商品の使用により得られた利益」は請求することがで
きません(法第35条の3の10第11項)。ここで、「商品の使用」には、「消耗
品の消費」も含まれるか否かが問題となりますが、私見としては、「商品の使
用」には「消耗品の消費」は含まれず、「消耗品の消費」により得られた利益
の返還の要否は、民法第 703条の現存利益の存否により判断すべきものと考え
ます。
c、適用除外
営業のため若しくは営業として締結する場合(連鎖販売個人契約、業務提供
誘引販売個人契約を除きます)、自動車その他特商法でクーリングオフの適用
除外とされる取引は、適用除外とされます(法第35条の3の60第1項第1号、
第4項)。
7、著しい過量販売に係る個別クレジット契約の申込みの撤回等
a、申込みの撤回等の制度
申込者等は、訪問販売であってその日常生活において通常必要とされる分量
を著しく超える商品の販売契約等に係る個別クレジット契約の申込みの撤回又
は解除を行うことができます(法第35条の3の12)。
この申込みの撤回等がなされるのは、訪問販売(いわゆるキャッチセールス、
アポイントメントセールスを含みます)に係る個別クレジット契約の場合に限
られ、訪問販売が特商法第9条の2第1項各号に当たる場合です。「分量」が
問題とされ、金額の多寡は割販法の与信限度の問題とされます。個別クレジッ
ト契約の申込みの撤回等を行えるのは、個別クレジット契約締結時から1年以
内です(法第35条の3の12第2項)。
b、著しい過量販売について
訪問販売に係るその日常生活において「通常必要とされる分量を著しく超え
る商品・指定権利の販売」「通常必要とされる回数、期間若しくは分量を著し
く超える役務の提供」については、その販売契約等の申込みの撤回等を行うこ
とができます(特商法第9条の2第1項)。
「通常必要とされる分量を著しく超える」取引としては、次の3つの類型が
あります。
(1) 一事業者が一回の取引で著しい過量販売を行う場合(第1号)
(2) 一事業者又は複数事業者が累積で著しい過量販売を行う場合(第2号前半)
当該取引で著しい過量販売になる場合をいい、事業者が著しく超えるこ
ととなることを知っていることが、要件とされます。
(3) 一事業者又は複数事業者が累積で著しい過量販売を行う場合(第2号後半)
既に著しい過量販売状態になった後の契約をいい、事業者が既に著しく
超えていることを知りながら契約することが、要件とされます。
「分量」を合計するのは、同一ないし同種の商品等についてです。「通常必
要とされる」の要件は客観的に判断されますが、商品等の種類・性質、取引実
態等のほか、家族構成といった消費者サイドの事情も考慮の対象となると考え
られます。上記(2)(3)の主観的要件の立証責任は、消費者にあります。
ただし、申込者等に当該訪問販売契約の締結を必要とする「特別の事情」が
あったときはこの限りでないとされています(法第35条の3の12第1項但書)。
特別の事情の例としては、「親戚に配る目的」「一時的に居宅における生活者
の人数が増える」等の事情が示されていますが、この「特別の事情」の立証責
任は、事業者にあります。
なお、申込者等が法定書面を受領した場合で政令指定された消耗品を消費し
たときは、クーリングオフでは適用除外とされていますが(法第35条の3の60
第1項第4項第3号)、著しい過量販売の申込みの撤回等では適用除外とされ
ていません。
c、「過量販売」と「著しい過量販売」
用語の問題ですが、「過量販売=通常必要とされる分量を超える商品の販売
契約等」と「著しい過量販売=通常必要とされる分量を著しく超える商品の販
売契約等」は、区別すると分かりやすいと考えます。
そこで、訪問販売取引は、次の3段階に分けられます。
(1) 「過量販売」に当たらない取引
(2) 「過量販売」には当たるが、「著しい過量販売」には当たらない取引
(3) 「著しい過量販売」に当たる取引(申込みの撤回等の対象となる取引)
ここで、「著しい」の要件が重要となりますが、「過量販売」「著しい過量
販売契約」は、分量を基準としていますので、「著しい」の要件は、倍率で示
される可能性があります。その場合、商品等の種類・性質、取引実態等に基づ
き、通常必要とされる分量の3~5倍程度が検討される可能性がありますが、
いずれにしても、今後の司法判断が注目されます。
d、申込みの撤回等の対象
申込みの撤回等の対象は、契約単位とされます。そこで、例えば、「A契約
+B契約」では、著しい過量販売には当たらないが、「A契約+B契約+C契
約」で著しい過量販売に当たることとなる場合は、原則として、C契約のみを
申込みの撤回等できると考えられます(参考判例:大阪地裁平成20年1月30日
判決)。これに対し、訪問販売業者が、当初から、著しい過量販売を行うこと
を目的として、「A契約+B契約+C契約」をした場合、
(1) C契約を行うことにより著しい過量販売に当たることとなる場合に、申込
みの撤回等を行うことができるのは、やはり、C契約のみが原則ですが、
著しい過量販売を行うことを目的として契約した場合は、いわゆる次々販
売とされ、得意客について特商法第4条~第10条を適用除外とする規定(
特商法第26条第5項第2号)は適用されませんので(特商法施行令第8条
第2号、第3号)、もし、訪問販売業者が、書面を交付していなければ、
クーリングオフの起算日がないとして、クーリングオフできるケースがあ
りえます。なお、ここで、「著しい過量販売を行うことを目的としていな
いこと(特商法施行令第8条第2号、第3号)」と「特別の事情があった
とき(特商法第9条の2第1項但書)」とは、ほぼ同内容と考えられます
ので、C契約について、「特別の事情(特商法第9条の2第1項但書)」
が認められる時は、「著しい過量販売を行うことを目的としていない」と
して、得意客について特商法第4条~第10条を適用除外とする規定(特商
法第26条第5項第2号)が適用されるケースが多いと考えられます。
(2) 他方、実質的に、「A契約+B契約+C契約」の全体が1個の契約と評価
される場合(例えば、形だけ契約を分割した場合等)は、全体について、
申込みの撤回等を行うことができるというケースもありえるでしょう。
しかして、上記の関連で、A契約ないしB契約は、どこまで溯って考えるか
については、一般的な基準はありません。例えば、消耗品の「A契約ないしB
契約」と「C契約」との間に相当の期間があいている場合などでは、いわゆる
一連の次々販売とは評価されないケースがありえます。そこで、「A契約+B
契約+C契約」で著しい過量販売に当たることとなるか否かは、商品等の種類
・性質、取引実態等に基づき、個別事案ごとに判断されるものと考えられます。
e、清算方法
著しい過量販売の場合の個別クレジット契約について申込みの撤回等があっ
た場合の清算方法(法第35条の3の12第4項~第6項)については、次のとお
り、販売契約等のクーリングオフ又は著しい過量販売の申込みの撤回等との先
後により異なります。
(1) 本条による個別クレジット契約の申込みの撤回等が、販売契約等のクーリ
ングオフ又は著しい過量販売の申込みの撤回等より先ないし同時に行われ
た場合
①すでに立替払金が加盟店に交付をされている場合であっても、個別ク
レジット業者は、その立替払金や手数料等に相当する金銭の支払を消費
者に請求することはできません(法第35条の3の12第4項本文)、②加
盟店である販売業者等は、すでに立替払金の交付を受けているときは、
立替払金を個別クレジット業者に返還しなければなりません(同第5項
本文)、③個別クレジット業者は、消費者に対して、既払金を返還しな
ければなりません(同第6項本文)。
(2) 販売契約等のクーリングオフ又は著しい過量販売の申込みの撤回等が、本
条による個別クレジット契約の申込みの撤回等より先になされた場合
販売業者等は、民法の原状回復義務ないし特商法第9条の2第3項、第
9条第6項により、立替払金を含む販売代金等を消費者に返還すること
になりますので、消費者は、それを前提に、個別クレジット業者との間
で、清算することになります(同第4項但書、第5項但書)。
f、その他
店舗販売(訪問販売の特定顧客を除く)やカード取引の場合は、著しい過量
販売によるクレジット契約の申込みの撤回等はありませんが、支払能力を大幅
に超えることとなった後の販売契約等は、公序良俗違反として無効とされ、抗
弁の接続がなされる可能性がありえます。
8、個別クレジット契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消
a、取消制度
購入者等は、特定契約に係る個別クレジット契約の締結について勧誘を受け
た際、重要事項につき、不実を告げられたことにより当該告げられた内容が事
実であると誤認し、又は、故意に事実を告げられなかったことにより当該事実
が存在しないと誤認し、これらによって当該契約の申込み又はその承諾の意思
表示をしたときは、これを取消すことができます(法第35条の3の13~16)。
特定契約以外の取引については、健全な取引に対する過剰規制となる恐れもあ
ることから、この取消の対象とはされていません。以下、訪問販売又は電話勧
誘販売に係る個別クレジット契約について記しますと、ここで、重要事項には、
「商品の種類・性能・品質、権利・役務の種類・内容その他購入者等の判断に
影響を及ぼすこととなる重要なもの」「商品の引渡時期、権利の移転時期、役
務の提供時期」「販売契約等の解除に関する事項」「その他、販売契約等に関
する事項であって、購入者等の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」(
法第35条の3の13第1項第3~6号。但し、6号は、不実告知のみ)、すなわ
ち、個別クレジット契約とは別個の販売契約等に関する事項(個別クレジット
契約締結の動機を構成する事項)も含まれることがポイントとなります。
b、取消の効果
個別クレジット契約が本条により取消され、かつ、販売契約等が取消その他
の事由により初めから無効である場合は、①個別クレジット業者は、立替払金
に相当する金額の支払を消費者に請求することはできません(法第35条の3の
13第2項)、②販売業者等は、個別クレジット業者から受領した立替払金相当
額を個別クレジット業者に返還しなければなりません(同第3項)、③消費者
は、個別クレジット業者に対して、既払金の返還を請求することができます(
同第4項)。