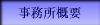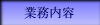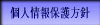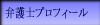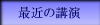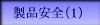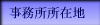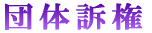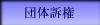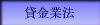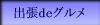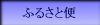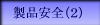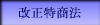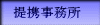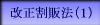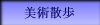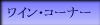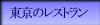消費者契約法の改正と消費者団体訴権の導入(平成19年6月7日施行)
高 芝 法 律 事 務 所
弁護士 高 芝 利 仁
1、消費者団体訴訟制度
A、適格消費者団体
差止請求関係業務を行おうとする者は、内閣総理大臣の認定を受けな
ければならない(消契法第13条第1項)
消費者利益代表性、訴権行使基盤が備わっていることを認定する
公正かつ透明な手続に基づいて、あらかじめ行政が適合性を
判断する
B、認定の申請、申請に関する公告・縦覧等
(1) 適格消費者団体の認定を受けようとする者は、名称及び住所、法人の
社員数等所定の事項を記載した申請書等を、内閣総理大臣に提出しな
ければならない(消契法第14条)
(2) 内閣総理大臣は申請書類等を公告・縦覧に供するとともに、必要に応
じ警察庁長官の意見を聴取(消契法第15条)
遅滞なく公告
公告の日から2週間、公衆の縦覧に供する
C、認定
内閣総理大臣は、申請をした者が次に掲げる要件のすべてに適合して
いるときに限り、その認定をすることができる(消契法第13条第3項)
①特定非営利活動法人又は民法第34条に規定する法人であること
法人格の取得を要件としている
「民法第34条に規定する法人」は「一般社団法人又は一般
財団法人」に改められる予定
ネットワーク組織を中心に8団体ほどが申請を検討して
いることのこと
②消費生活に関する情報の収集及び提供並びに消費者の被害の防止及
び救済のための活動その他の不特定かつ多数の消費者の利益擁護を
図るための活動を行うことを主たる目的とし、現にその活動を相当
期間にわたり継続して適正に行っていると認められること
消費者全体を代表するに値する団体であることを要件としている
活動 消費生活相談、 110番活動、消費生活情報の分析
・評価、啓発活動等(ガイドライン)
相当期間 原則、2年以上(ガイドライン)
適正 合理的な根拠に基づく真摯な活動(ガイドライン)
③差止請求関係業務の実施に係る組織、業務の実施の方法、業務に関
して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法その他の差止請求関
係業務を適正に遂行するための体制及び業務規程が適切に整備され
ていること
ガイドラインでは、社員数は、少なくとも、 100人以上
④差止請求関係業務の執行決定機関として理事会が置かれ、決定方法
が適正であること
適正性を確保
常任理事会への委任は認められない
理事のうちに占める特定の事業者の関係者又は同一業種の関係者の
割合が、それぞれ3分の1又は2分の1を超えていないこと
事業者との独立性あるいは差止請求権の適正性
適正な差止請求の行使を担保
⑤差止請求に係る検討部門において、専門委員(消費生活に関する専
門家、法律に関する専門家)が助言し意見を述べる体制が整備され
ていること
専門性を確保
体制の整備(しかし、専従スタッフという趣旨ではない)
消費生活に関する専門家(規則第4条第1号)
消費生活専門相談員、消費生活アドバイザー、消費生活コ
ンサルタントのいずれか(1年以上業務に従事)等
法律に関する専門家(規則第5条)
弁護士、司法書士、教授、准教授等
⑥差止請求関係業務を適正に遂行するに足りる経理的基礎を有すること
訴権行使基盤
⑦差止請求関係業務以外の業務を行う場合には、差止請求関係業務の
適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと
D、欠格事由(消極的要件)
弊害排除
(1) 暴力団員等がその事業活動を支配する法人、暴力団員等をその業務に
従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
(消契法第13条第5項第3号、第4号)
(2) 政治団体(消契法第13条第5項第5号)
E、認定の有効期間
認定の有効期間は、当該認定の日から起算して3年とする(消契法第17条第1項)
更新
訴訟の審理機関からして、訴訟中に更新時期がくることが想
定される
F、監督
(1) 財務諸表等の作成、備置き、閲覧等・提出等(消契法第31条)
①適格消費者団体の事務所には、財務諸表等、寄附金に関する事項等
を記載した書類等、所定の書類を備え置かなければならない
徹底した情報公開措置
②適格消費者団体は、毎事業年度、その業務がこの法律の規定に従い
適正に遂行されているかどうかについて、必要な学識経験を有する
者の調査を受けなければならない
(2) 報告・立入検査、適合命令・改善命令(消契法第32条、第33条)
行政処分
(3) 認定の取消し等(消契法第34条)
内閣総理大臣は、適格消費者団体について、次のいずれかに掲げる
事由があるときは、認定を取り消すことができる
①認定要件のいずれかに適合しなくなったとき
②欠格事由のいずれかに該当するに至ったとき
③事業者等と通謀して請求の放棄又は不特定かつ多数の消費者の利益
を害する内容の和解をしたとき、その他不特定かつ多数の消費者の
利益に著しく反する訴訟等の追行を行ったと認められるとき
G、差止請求権
(1) 適格消費者団体は、事業者等が不特定かつ多数の消費者に対して、消
費者契約法第4条第1項~第3項に規定されている不当な勧誘行為又
は同法第8条から第10条までに規定する不当な契約条項を含む契約の
締結の意思表示を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該行為の
差止請求をすることができる(消契法第12条第1項~第4項)
①第4条(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)第1項~第3項
不実告知、断定的判断の提供、有利事実の告知・不利益事実の
不告知、不退去型の困惑、監禁型の困惑
ビラや広告の不実文言は、「勧誘」とされない
電話による困惑は、「不退去型」「監禁型」に当たらない
②第5条(媒介の委託を受けた第三者及び代理人)
受託者等を利用して利益を得ている委託者である事業者等に対
して、間接的な差止請求(消契法第12条第2項)
③第8条(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
債務不履行 全部免除は無効
故意又は重過失による債務不履行 一部免除は無効
不法行為 全部免除は無効
故意又は重過失による不法行為 一部免除は無効
瑕疵担保 全部免除は無効
但し、代物、修理、他の事業者が全部又は一部の損
害賠償若しくは代物又は修理をする場合は、有効
④第9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
当該事業者に生ずべき平均的な損害の額
金銭債務について、14.6%
⑤第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法第1条第2項(信義誠実の原則)
⑥「不特定かつ多数の消費者」「行うおそれがあるとき」の要件
(2) 想定される主文のイメージ
「別紙目録記載の条項を含む契約を、不特定かつ多数の消費者との
間で行ってはならない」
「少なくとも、金○○円を超える違約金を定める条項を使用してはならない」
(3) 積極的な条項改訂請求はできない
「違約金額を金○○円に改めよ」という主文は相当でない
(4) 民法上の詐欺、強迫、公序良俗違反等は、対象とされない
今回は、消費者契約法の改正による消費者団体訴権の導入
(5) 事業者団体が、モデル約款、標準約款を推奨する行為は差止の対象と
はされない
(6) 事業者の業務自体の停止を求めるものではない
H、差止請求権の行使
(1) 適格消費者団体は、不特定かつ多数の消費者の利益のために、差止請
求権を適切に行使しなければならず、それを濫用してはならない(消
契法第23条第1項、第2項)
消費者利益代表性
(2) 適格消費者団体は、事案の性質に応じて他の適格消費者団体と共同し
て差止請求権を行使するほか、差止請求関係業務について相互に連携
を図りながら協力するように努めなければならない(消契法第23条第3項)
適格消費者団体間の不一致による弊害を除去
(3) 適格消費者団体は差止請求に関する所定の手続に係る行為について、
電磁的方法等により、他の適格消費者団体に通知し、内閣総理大臣に
報告しなければならない(消契法第23条第4項)
他の適格消費者団体が訴訟に参加することができる
I、差止請求ができない場合(消契法第12条第5項、第6項)
①当該適格消費者団体若しくは第三者の不当な利益を図り又は当該事
業者等に損害を加えることを目的とする場合
②他の適格消費者団体による差止請求に係る訴訟等につき既に確定判
決等(確定判決及び確定判決と同一の効力を有するものをいう)が
存する場合において、請求内容及び相手方である事業者等が同一で
ある場合
但し、後に生じた事由に基づいて差止請求をすることは妨げない
目的
矛盾判決の併存、事業者等の過大な応訴負担、訴訟不経済
等の弊害排除
複数の適格消費者団体が併存することが予定されることを前提
に、差止請求権そのものに制約を設けた
実質的な事実上又は法律上の争点が重複するケース
同一被告に対する同一事件について、他の適格消費者
団体が再訴することは、紛争の蒸し返し
請求内容の同一性
社会的事実の同一性及び差止請求権の根拠となる法規の同一性
「後に生じた事由」
例えば、業界慣行が変化した場合、判例変更があった場合、
不特定かつ多数性が認められるようになった場合
J、差止請求訴訟提起前の事前請求(消契法第41条第1項)
適格消費者団体は、被告となるべき事業者等に対し、あらかじめ、請
求の要旨及び紛争の要点等を記た書面により差止請求をし、その到達
時から一週間経過した後でなければ、差止めの訴えを提起することが
できない(事業者等がその差止請求を拒んだときは、この限りではない)
自ら是正する機会を与える
これにより、紛争の早期解決と取引の適正化を図る
K、差止訴訟の手続
訴訟手続について、原則、民事訴訟法の規定に従いつつ、制度の特色
を踏まえ、所要の措置
①訴額(消契法第42条)
財産権上の請求でない請求(訴額は160万円とされる)
印紙は、13,000円
②管轄(消契法第43条)
事務所又は営業所の所在地
事業者等の行為があった地
③移送(消契法第44条)
同一又は同種行為の差止請求訴訟が併存する場合
重複訴訟はなるべく認めない
④弁論等の併合(消契法第45条第1項)
請求内容及び相手方である事業者等が同一である差止請求訴訟が
同一裁判所に係属する場合
重複訴訟はなるべく認めない
⑤間接強制の支払額の算定(消契法第47条)
債務の履行を確保するために相当と認める一定額の金銭(間接強
制金)を定めるに当たっては、債務不履行により不特定かつ多数
の消費者が受けるべき不利益を特に考慮しなければならない
L、財産上の利益の受領の禁止等(消契法第28条)
適格消費者団体は、訴訟費用、間接強制金等を除き、差止請求に係る
相手方から、その差止請求権の行使に関し、寄附金、賛助金その他名
目のいかんを問わず、金銭その他の財産上の利益を受けてはならない
差止請求権の行使をしないこと若しくはしなかったこと等の報酬
として、金銭その他の財産上の利益を受け又は第三者に受けさせ
たときは、3年以下の懲役又は 300万円以下の罰金(消契法第49条第1項)
本制度は、不特定かつ多数の消費者の利益擁護のため
適格消費者団体の利益獲得のためではない
M、規律(消契法第36条)
適格消費者団体は、政党又は政治的目的のために利用してはならない
N、判決等に関する情報の公表(消契法第27条、第39条)
適格消費者団体は、消費者に対し、差止請求に係る判決や裁判外の和
解の内容その他必要な情報を提供するように努めなければならない
内閣総理大臣は、インターネットの利用等により、速やかに、判決、
裁判外の和解の概要等を公表する
このほか、内閣総理大臣は、差止請求関係業務に関する情報を広く国
民に提供する
O、適格消費者団体への協力等(消契法第40条)
国民生活センター及び地方公共団体は、適格消費者団体の求めに応じ、
必要な限度において、消費生活相談に関する情報を提供することがで
きる
2、その他
A、援用制度(使用が差止められた条項を含んだ過去の契約の条項の無効を
個別訴訟で主張できる制度)は導入されなかった
← 個々の消費者被害を救済するものではない
無効が推定される可能性(立証責任が転換される可能性)
権利主張が信義則違反とされる可能性
B、損害賠償は、対象とされない
消費者団体訴訟制度の目的は、同種紛争の未然防止、拡大防止
利得の吐き出しとしての金銭請求の仕組みは、対象とされない
被害を受けた個々の消費者は損害賠償請求権を有している
少額訴訟制度の拡大、簡易裁判所の機能の充実等で対応
C、他の法律への導入
特定商取引法への導入の検討
2005年4月の消費者基本計画には、独占禁止法及び景品表示法におけ
る団体訴権の導入の検討が記載されている